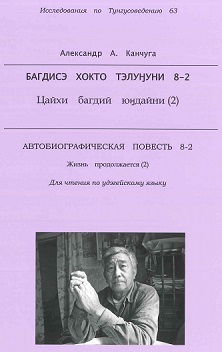 彼の少年時代の記述が読む者の胸を打つのは、もちろん著者のみずみずしくあたたかな眼差しとすぐれた描写によるところが大きいが、そればかりでなく、そこに描かれている出来事がほんの数十年前に確かにあった、という事実の重みがもつ意味もまた大きいのではないだろうか。豊かな自然と、戦時をはさんだ窮乏生活、そのなかで育まれる親子や兄弟の絆には共感を覚える世代も多いに違いない。忘れかけていた昔の暮らし、といってもちょっと前まではごくふつうだったはずのことをあらためて思い起こした、という感想を聞かせてくれた人も多かった。環境は違っても、人々の日々の暮らしや肉親の情には相通じるものがあるということだろう。もちろん北方民族ならではの生業や精神生活に対しても、子どもの素直な目で見た観察が克明に記録されていて、その点で民族自身が語る「自分史」の形をとった、新しい形の民族誌、生活史だ、という見方もできよう。
彼の少年時代の記述が読む者の胸を打つのは、もちろん著者のみずみずしくあたたかな眼差しとすぐれた描写によるところが大きいが、そればかりでなく、そこに描かれている出来事がほんの数十年前に確かにあった、という事実の重みがもつ意味もまた大きいのではないだろうか。豊かな自然と、戦時をはさんだ窮乏生活、そのなかで育まれる親子や兄弟の絆には共感を覚える世代も多いに違いない。忘れかけていた昔の暮らし、といってもちょっと前まではごくふつうだったはずのことをあらためて思い起こした、という感想を聞かせてくれた人も多かった。環境は違っても、人々の日々の暮らしや肉親の情には相通じるものがあるということだろう。もちろん北方民族ならではの生業や精神生活に対しても、子どもの素直な目で見た観察が克明に記録されていて、その点で民族自身が語る「自分史」の形をとった、新しい形の民族誌、生活史だ、という見方もできよう。
ちりばめられた何気ないエピソードの一つ―つにも事実の重みがある。たとえばカンチュガ少年12歳の夏、父・兄とタイガに狩に出ていてナイフで怪我をする場面がある。ウデヘ語でアフィリ(afili) という、このナイフがどんな形でどう使うのか、著者に尋ねてみたところ、実物がある、と言って見せてくれた。細長く湾曲した小ぶりの刃に、硬い木の柄がついている。永年使い込んだらしく、黒光りしていてしっくりと手になじむ。いかにも使った人の愛着を感じさせた。イノシシ皮の鞘もついている。刃が湾曲しているのはもっぱら木を削るためで、錐のようにとがった刃先で穴をあけることもできるという。その場でペチカの薪を削ってみせてくれたが、今もよく切れる。だれがいつ作ったものか尋ねると父が使っていたもので、多分父自身が作ったものという。50年以上前、彼に傷を負わせたのもおそらくこのナイフだろう、と聞いて、モノが時間を超えて事実を伝えることを実感した。おまけに彼はズボンをおろして、太ももに今も残る傷跡まで見せてくれた。
実はかねてから、調査のついでに何かウデヘの民具でも収集できたら、と考えていた。博物館に買い上げてもらえば、博物館の収集にも協力できるし現地の人にも還元できるだろう。このナイフを見て、そんな思いが頭をかすめたが「譲ってほしい」とは言い出せなかった。思い出のこもった、父の形見のナイフをなにがしかの金と引き換えたところで、彼は思い出のよすがを失い、博物館はナイフに込められた歴史と思いまでは買い取れないだろう。少なくとも彼が生きている限り、彼の手元にあるのがふさわしい、と思ったのだ。
言うまでもなく、博物館に収蔵・展示されているモノたちにはみなそれぞれの歴史と、作り手や使い手の思いがあったに違いない。博物館に展示されることで「個別」のモノが「一般化」してしまうのは避けがたいことでもある。しかしそうした、記録に残りにくい「個別性」を切り捨てずにできるだけ大事に扱うのが、実は博物館の使命の一つなのかもしれないし、見る側もモノに込められた思いを読み取る姿勢が大切なのだろう。
そんなことを考えさせられたのも、彼の物語をとおして、これが12歳のカンチュガ少年の血を流した「あのナイフ」だとわかったからだ。モノにそれぞれ歴史があるように、人にもみな物語がある。その人の物語を知れば、その人自身にはもちろん、その人にかかわった人々にもモノにも出来事にも何かしらの「親しさ」あるいは「いとおしさ」と言ってもいいような気持ちを覚えるものだ。
カンチュガ氏と出会い、彼の自分史と出会ったのも思えば不思議な偶然だが、この出会いを大切にして、彼の物語が続く限り、かかわっていきたいと考えている。

